なぜ、変革の取り組みが成果に結びつかないのか?―『プロセス・コンサルテーション』が示す変革者に必要な知性 ――宇田川元一さんインタビュー
 長期的な低迷に加え新型コロナウイルスの追い打ちを受け、日本経済は深刻な状況に陥っている。多くの企業や自治体で変革への挑戦が行われているが、十分な成果が得られているとは言い難い。そもそも失われた20年の最中も変革の必要性が叫ばれてきたが、その結果が低迷続きの現状である。なぜ、変革の取り組みが成果に結びつかないのか。経営戦略論、組織論を専門とする埼玉大学の宇田川元一准教授はこの問題を考える上で、エドガー・シャインの『プロセス・コンサルテーション』が大いに示唆を与えてくれるという。
長期的な低迷に加え新型コロナウイルスの追い打ちを受け、日本経済は深刻な状況に陥っている。多くの企業や自治体で変革への挑戦が行われているが、十分な成果が得られているとは言い難い。そもそも失われた20年の最中も変革の必要性が叫ばれてきたが、その結果が低迷続きの現状である。なぜ、変革の取り組みが成果に結びつかないのか。経営戦略論、組織論を専門とする埼玉大学の宇田川元一准教授はこの問題を考える上で、エドガー・シャインの『プロセス・コンサルテーション』が大いに示唆を与えてくれるという。
(聞き手 宮内 健)
従来型のコンサルテーションとの違いとは?
――シャインの『プロセス・コンサルテーション』をどう評価されていますか。
宇田川 本書の冒頭でシャインはコンサルテーション・モデルを「情報-購入型 すなわち専門家モデル」と「医師―患者モデル」、そして「プロセス・コンサルテーション・モデル」の3つに分類し、プロセス・コンサルテーション・モデルは前二者とは大きく異なると主張しています。その違いとは、前二者はコンサルテーション側が答えを持っているのに対し、後者は持っていない点です。これは非常にユニークかつ現実的な見解だと共感しています。コンサルテーションを広く支援と捉えた時、既にある答えを与えたり診断したりする従来型のコンサルテーションとプロセス・コンサルテーションは違うというわけです。
シャインはプロセス・コンサルテーションの10個の原則を掲げていて、どれも素晴らしいのですが、中でも原則3の「あなたの無知にアクセスせよ。」は重要で、面白いと思います。要は「自分がわかっていないことは何かを考えよ」と言っているわけで、非常に実践的です。世の中では「実践的」という言葉が不思議な使われ方をしています。私はMBAで教員をしていますが、学びにきている学生はケーススタディの答えを以って実践的と思い込んでいる人が少なくありません。あるいは書店に行くと、個人の経験を整理しただけのハック本(編注:ビジネスノウハウを手っ取り早く学べる本)が科学的なふりをして山ほど売られています。やはり皆さん、すぐ役に立ちそうな答えを欲しがっているようですが、それは本当に実践的なのかといえば非常に疑問です。
自分が今欲しいものを手に入れることが願望だとすると、願望が叶わなくてもその先に何かが開かれることを待っている、自分の準備ができている感覚が希望だと私は考えています。その意味ではシャインは願望ではなく希望を我々が手に入れるための方法論として、プロセス・コンサルテーションを展開していると言えます。支援を求めているクライアントに対し、答えを持っているかどうかではなく、「あなたはこの答えが欲しいと言っていますが、それは何の必要からでしょうか?」という地点からスタートする、願望ではなく希望にアクセスする方法論を切り開いたという点を私は評価しています。
既存の答え探しが変革の挫折を招く
――宇田川先生の研究分野とシャインにはどのような関連がありますか。
宇田川 私自身は医療や臨床心理の領域で研究・実践されてきた「ナラティヴ・アプローチ」に軸足があり、これを経営学や経営の実践にどう取り入れていくかに研究上の関心があります。ナラティヴには2つの意味があり、一つは語る行為である「語り」、もう一つはその語りを生み出す会社の枠組みとしての「物語」で、シャインはナラティヴ・アプローチそのものの研究者ではありませんが、考えていることはかなり近いと思っています。
今私がやりたいのは、広義の経営の実践においてケアの思想を取り入れていくことです。ケアとはその人にとって必要なことは何かを見つける支援を行い、そのことを通じて自分が支援されることを言い、企業変革やイノベーションの推進について、私自身も実践に踏み込んで関与しています。成果物を提供する一般的なコンサルティングとは異なる関わり方ですが、その現場で起こっているのは「何をやったらよいのかよくわからない」状況です。その時、多くの人は既に世の中にある答えを使って解決しようとするのですが、それではまったくうまくいきません。うまくいかない原因は、自分たちが何に困っているのか、何を必要としているのかをわからないまま、手っ取り早く手に入る解決策に飛びつくところにあります。
理屈は整っているんです。Rational(理にかなった)ではあるんですが、Reasonable(妥当)ではない。よく「Whyを問え」と言われますが、私はReasonを問うたほうがよいと思います。要するに、自分は何をやっていて何に困っているからこれが必要だというReasonがない状態、すなわち身体性を伴わないまま解決に突っ走ってしまうからうまくいかないのです。その意味では現在流行しているDX(デジタル・トランスフォーメーション)も過去に流行った経営手法と同じような失敗が繰り返されるだろうと容易に想像がつきますが、プロセス・コンサルテーションはこの問題をきちんと解きほぐしています。
「あなたの無知にアクセスせよ。」が重要である理由
――ただ、組織変革の必要性が認識され、プロセス・コンサルテーションのような考え方はある程度、認知されてきたと思いますが、なかなか成果には結びついていないようにも思います。どこに問題があるのでしょうか。
宇田川 組織変革では組織文化や関係性の質を変えようといった話になりがちですが、みんなが困っているのはそこではない、ということです。例えば「変革には対話が大事だが、現場のマネージャーが対話に参加してくれない」と悩む人事は、対話が正しい手段であり現場マネージャーは参加すべきであると考えていますが、それは対話の顔をした、対話とはまったく別のものです。まずやるべきは相手にとって何が必要なのかを考えることであり、「あなたの無知にアクセスせよ。」というシャインの言葉の重要性がそこにあります。
『組織化の社会心理学』を書いたカール・ワイクは、組織は実態としてあるのかないのかよくわからない存在で、組織(organization)ではなく組織化(organizing)という活動があるのだと指摘しています。確かに大学に行っても、私は大学という組織を見たことがありません。これに従えば組織を変えようとするのではなく、活動を変えていくことにもっと目を向けたほうがよい。目の前で起きていること、たとえば「なぜ役員は方針を示してくれないのか」、「競合の出現で売上が下がっているのに部下に危機感がない」といった具体的な事象と向き合って、自分にできることから始めてみる。その営みを継続し、ある程度時間が経過してから振り返ってみると組織が変わったように見えるだけであって、組織がないのに組織を変えようとすること自体、問題設定がおかしいのだと思います。
「組織を変える」というのは、「世界を変える」というのに近い。それよりも、自分が生きている世界を自分にとって意味のあるものにするためにはどこから手を付ければよいのかを考える。つまり、こちら側が正しくて、正しくない向こう側の世界を変えようとするのではなく、自分も問題の一部であり、自分が今までと同じことをすると同じ問題が繰り返されるつながりを見付け、自分なりにできる行動を起こしていく。別の表現をすると、自分と世界のつながりを変えていくことが、本当に世界を変えたいのならば重要である、と言えるでしょう。
なぜ的外れな変革プロジェクトが生まれるのか
――変革には対話が重要とよく聞くようになりましたが、単なる雑談に終始したり、その後のアクションにつながらなかったりと、空回りするケースも見受けられます。
宇田川 数人が集まって話をすればなんとかなる、というほど簡単なものではありません。対話のプロセスは「溝に橋を架ける」行為になぞらえることができます。私の整理では、そのプロセスは「溝に気付く」準備、「溝の向こうを眺める」観察、「溝を渡り橋を設計する」解釈、「溝に橋を架ける」介入の4つに大きく分けられます。「なぜ役員が方針を示さないのか、自分は分かっていない」と自覚するのが準備で、その上で相手を観察し、観察から見えてきたことを解釈し、「方針を示さないのはこういう理由ではないか」と分かってきたら最後に介入するわけです。
人は自分が生きているナラティヴはなかなか分からないものですが、他人の偏りにはすぐ気付きます。ということは、自分も偏っているはずなのですが。リチャード・ローティというアメリカの哲学者は、自分の偏りから出発して連帯を築く過程が対話であると言っています。とすれば、自分に偏りがあると気付くことが対話の準備段階と言え、準備を整えないで話をしても対話にはなりません。
リーダーシップ論で著名なロナルド・ハイフェッツは既存の方法で解決できる問題を「技術的問題」、既存の方法では解決できない複雑で困難な問題を「適応課題」と定義しています。わかりやすく言うと、スマートフォンの性能が落ちたとき、お店に行って買い替えれば問題は解決します。これは技術的問題ですが、そのスマホが会社の支給品だと途端に解決が難しくなります。「スマホのバージョンが古いとこのアプリが使えないので買い替えて下さい」と総務部に説明しても、「会社の方針がコスト削減なので我慢して使って下さい」と埒が明かなかったりします。これが適応課題です。
 適応課題に直面したとき、まず必要なのは「なぜ自分の想定とは異なる反応が返ってくるのか」を考えることと、相手のナラティヴの観察です。しかし実際にはノーと否定されたことにムカッとしたり認められなかったりして、相手が観察する価値がある対象だとは受け入れられない事態がしばしば生じます。そして自分の正しさを証明するために、向こう側の世界を変えようとしてしまうことが起こってしまう。「あの人たちは理解していないが、私たちは本当に大事なことをやっています」、というような。しかし、ドラッカーを持ち出すまでもなく、成果を生み出せなければ存在し続けることは不可能で、成果を生み出すという軸を持たなければ意味がありません。
適応課題に直面したとき、まず必要なのは「なぜ自分の想定とは異なる反応が返ってくるのか」を考えることと、相手のナラティヴの観察です。しかし実際にはノーと否定されたことにムカッとしたり認められなかったりして、相手が観察する価値がある対象だとは受け入れられない事態がしばしば生じます。そして自分の正しさを証明するために、向こう側の世界を変えようとしてしまうことが起こってしまう。「あの人たちは理解していないが、私たちは本当に大事なことをやっています」、というような。しかし、ドラッカーを持ち出すまでもなく、成果を生み出せなければ存在し続けることは不可能で、成果を生み出すという軸を持たなければ意味がありません。
――自分が正しいと考えて行っている取り組みが、実は的外れである事態が生じてしまうと。
宇田川 薬物依存症が専門の松本俊彦先生によると、薬物やアルコールの依存症になる原因は日々つらいからだそうです。毎日がつらいから薬物やアルコールを摂取し続けてしまう。そうなると単に薬物やアルコールの摂取を止めるのではなく、日々つらい状況を少しずつ解消していくことが大切なアプローチになります。そうしたある種の依存症のような状況がビジネスの世界にはびこっていて、自分の正義を信じて取り組んでいるのにうまくいかずどんどん疲弊していくときは、本当は何か別のことに困っているかもしれないと気付くことが大切です。そこから別のアプローチが見えてきて、希望につながります。
今、必要なのは「慢性疾患的な変化」への対処
――プロセス・コンサルテーションは、企業で変革を実践している方にどんな寄与ができるでしょうか。
宇田川 日本はいま、衰退という近代化以降、初めての経験をしています。人口が減少し高齢化が進み、とくに地方は衰退が著しい。私も九州に9年間住んでいたときに、商店街が全部シャッター街になっている状況をよく目にしました。ただ衰退は確実に起きている変化ですが、非常に穏やかな変化なので人々の実感があまり伴いません。昨日と今日ではそれほど変わらないが、3年前と比べたらだいぶ悪化しているという、慢性疾患的な変化です。
ところがいま、変革論として取り上げられているのは急性疾患的な変化への対応ばかりです。「新型コロナ禍を変革の好機に」とよく言われますが、そんなコンサルタントのポジショントークに左右されず、真の変革者になるための知性が『プロセス・コンサルテーション』にはあります。言っていることは要するに「一歩ずつ進め」なので非常に地味ですが、一歩ずつ進めば着実に前進します。それを繰り返し続けることが、これからの日本の社会で求められる変革です。
倒産の危機に直面するような状況では急性疾患への方法論が必要ですが、そんな劇的な事態は頻繁に発生しません。実際に起きているのは売上高1兆円の企業が毎年、150億円ずつ売上が減少していくといった緩やかな危機です。だから一過性の危機感など必要なく、実践者が着実に変革をし続けることが重要で、その方法論の一つとなるのが『プロセス・コンサルテーション』だと思います。
(9月30日オンライン会議アプリを用い収録)

宇田川 元一(うだがわ もとかず)
埼玉大学経済経営系大学院准教授
1977年東京都生まれ。2000年立教大学経済学部卒業。2002年同大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。2006年明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。
社会構成主義の思想に基づき企業変革やイノベーション推進について研究を行っている。また、大手企業やスタートアップ企業で、イノベーション推進や組織変革のためのアドバイザーや顧問を務め、その実践を支援している。
専門は経営戦略論、組織論。著書に『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング)がある。

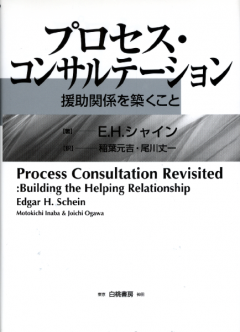 『プロセス・コンサルテーション』(白桃書房)
『プロセス・コンサルテーション』(白桃書房) 『組織化の社会心理学〔原書第2版〕』(文眞堂)
『組織化の社会心理学〔原書第2版〕』(文眞堂)