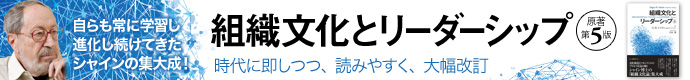『組織文化とリーダーシップ 原著第5版』刊行記念イベントレポート
去る2025年8月1日、小社白桃書房は、『組織文化とリーダーシップ 原著第5版』(E.H.シャイン、P.シャイン著)の刊行記念イベントを人事図書館様と共催いたしました。スピーカーとして、監修・監訳をご担当いただいた宇田理先生(青山学院大学経営学部教授)に登壇いただきました。
宇田先生はご専門がIT産業の経営史で、IT企業のエピソードなどを踏まえ、同書そして組織文化論について解説されました。
簡単にその内容をレポートします(白桃書房営業部)。
シャインの組織文化論:その本質と三階層モデル
 宇田先生は、多くのビジネスパーソンが組織文化について「カルチャー語り」をしがちで、理想とする行動規範やスローガンを文化と捉えがちだと指摘しました。しかし、文化の本質は、簡単には目標にそぐう形で変わらない点にあると強調しました。
宇田先生は、多くのビジネスパーソンが組織文化について「カルチャー語り」をしがちで、理想とする行動規範やスローガンを文化と捉えがちだと指摘しました。しかし、文化の本質は、簡単には目標にそぐう形で変わらない点にあると強調しました。
シャインの組織文化論の原点は、彼がミニコンピューターの会社DEC(デジタル・エクイップメント・コーポレーション)のコンサルティングに関わったことにあります。優秀な人材が集まっていたはずのDEC社では、会議が非生産的な大喧嘩に終わることが常態化していました。シャインは、会議の「中身(コンテンツ)」ではなく、その「進め方(プロセス)」に介入することで、コミュニケーションが円滑になることを発見しました。この経験から、組織を「臨床的」に捉える必要があるとともに、それぞれの組織には固有の文化が形成されるものだという考えに至りました。
文化を理解するために、シャインは三階層モデルを提唱しています。
人工物(Artifacts): オフィスのレイアウトや従業員の服装など、目に見えるものや行動。
価値観(Espoused Values): 経営理念や目標など、言語化された信念や価値観。
基本的前提(Basic Assumptions): 当事者にとって当たり前すぎて言語化されない、無意識下の価値観や信念。
この中でも、最も重要で変革が難しいのが文化の最深部にある「基本的前提」です。文化とは、組織が外部適応と内部統合の課題を解決していく過程で蓄積・共有された学習の産物であり、こうした組織化のプロセスを理解することなしに文化を変えることはできないと、宇田先生は説明しました。
リーダーシップと組織文化変革のポイント
また宇田先生は、リーダーシップと組織文化の関係について、企業の成長ステージごとに解説しました。
創業期: 創業者の個人的価値観や信念が文化の基盤となるため、文化を変える必要がない。
中年期: 組織が成長する中で、文化に合った信念を持つ後継者が重要となる。異なる文化を持つリーダーが就任すると、組織が混乱しがち。
Apple社のスティーブ・ジョブズとジョン・スカリーのエピソードが紹介されました。成熟期・衰退期: 組織にとって都合のいい神話や物語だけが残り、理念と現実が乖離していく危険性が高い。
成熟期・衰退期の課題を乗り越えるために、宇田先生が提唱したのが社内の「サブカルチャー探し」です。大規模な組織では部門や国ごとに多様な文化が存在するため、リーダーは組織内に残る「創業者の文化のエッセンス」を再発見し、それを再統合することが重要とのことです。
質疑応答
「組織文化は結局、原点に戻るしかないのか?」あるいは「共有された学習はどのようなプロセスで発生するのか?」といったような質問が出ました。宇田先生は、文化は常にダイナミックに変化するものであり、その変革には長期的な視点が必要だと回答しました。また、文化の変革を考える上で、組織を「臨床心理学的」に捉えるシャインの考え方、すなわち組織セラピーの視点も大切であると語りました。
翻訳の苦労と参加者へのメッセージ
 宇田先生は、翻訳の苦労についても触れました。難解な内容を「日本語でかなり理解できるように」するため、噛み砕いた用語とするなど努力を重ねたとのことです。例えば、Basic Assumptionを、以前の版では「基本的仮定」としていたところを「基本的前提」とするなど、シャインの意図を正確に伝えるための工夫を凝らしたとお話しされました。
宇田先生は、翻訳の苦労についても触れました。難解な内容を「日本語でかなり理解できるように」するため、噛み砕いた用語とするなど努力を重ねたとのことです。例えば、Basic Assumptionを、以前の版では「基本的仮定」としていたところを「基本的前提」とするなど、シャインの意図を正確に伝えるための工夫を凝らしたとお話しされました。
最後に、宇田先生は参加者に対し、「短期的な成果を求めがちな現代において、文化という長期的な視点を持つことの重要性」を強調しました。組織は常に変化する流動的な存在であり、リーダーは文化が成長ステージごとに進化していくプロセスを理解し、舵取りをしていかなければならないというメッセージで締めくくられました。
本イベントの感想
本イベントでは、吉田館長の司会・進行で行われ、和やかな雰囲気のなか、高いレベルの議論がなされました。組織文化に強い関心を集まっている方が集まっていることがうかがわれ、特に質疑応答では大変質の高いディスカッションを拝聴できました。個人的にも組織文化に興味を持っていましたので、大変勉強になりました。